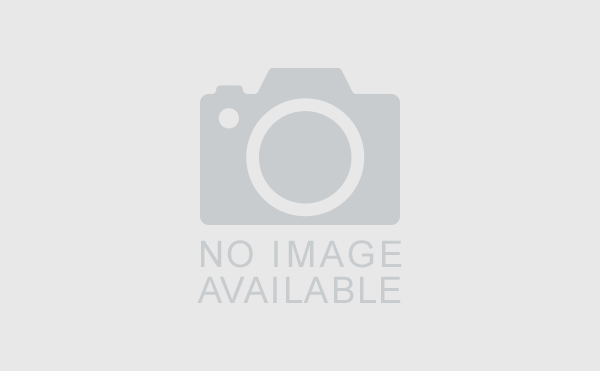【北海道の食品メーカー必見】台湾越境ECで「売れる商品」と「売れない商品」の決定的な違い
「北海道産の食材を使っているから、台湾でも間違いなく売れるはずだ」
もしあなたがそう考えているなら、少しだけ立ち止まってください。
確かに台湾において「北海道ブランド」の信頼性は絶大です。コロナ禍が明け、新千歳空港には多くの台湾人観光客が戻ってきました。しかし、「現地で人気があること」と「越境ECで継続的に売れること」は、全く別の話です。
私はこれまで、自社で立ち上げたD2Cブランドを売却まで導いた経験や、多くの道内企業の海外進出を支援する中で、「商品は良いのに、売り方を間違えて撤退するメーカー」を数多く見てきました。特に物流コストが重くのしかかる北海道の企業にとって、戦略のミスは命取りになります。
この記事では、北海道の食品メーカーが台湾越境ECで直面する現実と、利益を出して勝ち残るための「売れる商品の条件」について、現場の生々しいデータを交えて解説します。
台湾越境ECにおける「売れる商品」と「売れない商品」の決定的な差とは?
結論、現地のライフスタイルに合わせた「ローカライズ(現地化)」ができているかどうかが、成否を分ける最大の要因です。
「日本の味をそのまま届けたい」という職人魂は素晴らしいものですが、マーケティングの観点ではそれが足かせになることがあります。売れない商品の典型例は、日本のパッケージや規格をそのまま翻訳しただけの商品です。
なぜ「そのまま」では売れないのか
台湾の消費者は、日本の商品に対して「高品質」や「安心安全」を求めていますが、同時に彼ら独自の消費習慣があります。
例えば、私が過去にご相談を受けたある道内のスイーツメーカー様の事例です。
日本国内では「大容量のお得用パック」が飛ぶように売れていました。しかし、台湾でそのまま販売しても反応は鈍いまま。理由は明確で、台湾のECユーザー(特にShopeeなどを利用する層)は、自分へのご褒美や友人へのちょっとした「プチギフト」として購入する傾向が強かったのです。
具体例:パッケージ一つで売上が3倍になった事例
そこで私たちは、中身は変えずにパッケージを刷新しました。「大袋」から「個包装の小箱(3個入り)」に変更し、デザインも台湾で好まれるパステルカラーの可愛らしいものへローカライズしました。さらに、「オフィスの同僚に配るのに最適」という訴求でSNS広告を展開したところ、クリック率(CTR)は改善し、売上は以前の3倍以上に跳ね上がりました。
「売れる商品」とは、現地の生活の中に自然に溶け込める商品のことを指します。
「北海道ブランド」にあぐらをかくと失敗する理由
結論、北海道産であることはもはや「差別化」ではなく「参加資格」に過ぎないからです。
「北海道産=美味しい」という認知は、台湾市場において既に飽和状態にあります。デパートの北海道物産展は人気ですが、EC市場を見渡せば、ライバルは他の北海道企業だけでなく、日本全国、さらには現地の日本風商品とも戦わなければなりません。
埋もれないための「ストーリーテリング」
「北海道の牛乳を使っています」だけでは、数ある商品の中に埋もれてしまいます。売れる商品には、必ず「なぜ北海道の、その場所で作られたのか」という強力なストーリーがあります。
- × 一般的な訴求: 北海道の新鮮な生乳を使用したチーズケーキです。
- ○ 売れる訴求: 札幌から車で2時間。冬にはマイナス20度になる豪雪地帯の工房で、牛のストレスを極限まで減らして作られた「冬限定」の濃厚チーズケーキです。
このように、具体的な情景(シズル感)と希少性をセットで伝えることで初めて、現地のユーザーは送料の壁を越えて「指名買い」をしてくれます。AI翻訳や自動翻訳ツールを使っただけのECサイトでは、この熱量は絶対に伝わりません。
北海道の事業者が最も苦しむ「物流コスト」の壁と対策
結論、商品開発の段階で「送料負けしない規格」を設計するか、高単価でも納得させるブランディングを行うかの二択です。
私たち北海道の事業者にとって、津軽海峡を越え、さらに国境を越える物流コストは最大の課題です。クール便(冷蔵・冷凍)での越境ECは、配送品質の維持が難しく、コストも跳ね上がるため、利益率を著しく圧迫します。
常温商品へのシフトと「厚み」の調整
私がコンサルティングに入る際、最初に見直すのが「配送サイズ」です。
以前、ある海産加工品メーカー様が、立派な化粧箱に入れて商品を販売していました。しかし、その箱の厚みが航空便の特定サイズ区分を数ミリ超えていたため、送料が1段階高くなっていたのです。
私たちはパッケージの厚みを5mm薄くし、メール便や小型包装物でも送れるサイズにリニューアルすることを提案しました。これにより1件あたりの配送コストを数百円削減でき、その分を現地のKOL(インフルエンサー)施策への投資に回すことで、利益体質への転換に成功しました。
「作りたいもの」ではなく、「送っても利益が出るもの」を作ること。これがEC事業を継続させる鉄則です。
失敗しないための進出ステップ:いきなり自社サイトを作らない
結論、まずはShopee(ショッピー)などのモールや、現地のクラウドファンディングで「テスト販売」を行うべきです。
多くの制作会社は「越境ECサイトを作りましょう」と提案してきますが、集客力のない独自ドメインのサイトをいきなり立ち上げるのは、無人島にお店を出すようなものです。数百万かけてサイトを作ったのに、アクセスがゼロという悲劇を私は何度も見てきました。
Entechが推奨する「スモールスタート」戦略
- リサーチ: 競合商品の価格帯とレビューを徹底分析。
- テスト販売: Shopee台湾に出店し、広告費を抑えて反応を見る。あるいは台湾のクラウドファンディング(ZecZecなど)で予約販売を行う。
- 本格展開: テストで手応えがあった商品に絞り、自社サイト(Shopifyなど)を構築してリピーターを囲い込む。
この順序を守るだけで、大火傷をするリスクは劇的に下がります。私の経験上、最初のテスト販売でPDCAを回せた企業ほど、その後の生存率が高いです。
まとめ:北海道から世界へ。利益に残る越境ECを
台湾越境ECで成功するためのポイントをまとめます。
- ローカライズ: 日本の規格を押し付けず、現地の習慣に合わせる。
- ストーリー: 「北海道産」以上の付加価値と情景を伝える。
- 物流設計: 送料を計算に入れた商品サイズと常温対応を検討する。
- スモールスタート: いきなりサイト構築せず、モール等で需要を検証する。
越境ECは「サイトを作って終わり」ではありません。そこからがスタートです。
私たち株式会社Entechは、単なるサイト制作会社ではなく、皆様と同じ「事業主」としての経験を持つEC運用のプロフェッショナル集団です。
「自社の商品は台湾で通用するのか?」「AmazonとShopee、どっちから始めるべき?」
そのような疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。現在、毎月5社限定で「無料の越境EC診断・Amazonアカウント分析」を実施しています。
無理な売り込みは一切いたしません。北海道から世界へ挑戦する仲間として、まずは現状の課題を整理してみませんか?